倶楽部 原則
●清水組麻雀格闘倶楽部の主戦場は倶楽部のリーダー野村の家の2Fです。そこには全自動麻雀卓が2台完備してあります。この麻雀卓は倶楽部メンバーの有志5名が共同して出資したもので、出資メンバーを「オリジナル5」と称し倶楽部の開催日・ルール等を決定・変更する権利を有するモノとします。オリジナル5のメンバーは高須・キンキン・中川さん・りゅうじ・野村の五名です。
開催日
●毎週金曜日の21:00~
●不定期開催…オリジナル5のメンバーが麻雀したくなったらメンバーに連絡して面子が揃えば開催する事が出来ます。
会費
●オリジナル5…無料
●その他のメンバー…500円(時間無制限)
闘牌ルール
●4人一組で東南戦の半荘を一回戦とする。
●喰い断幺九・後付けあり。
●裏ドラ・槓ドラ・槓裏ドラあり。(槓ドラは槓子開示後、嶺上牌をツモる前に槓ドラ表示牌を表示)
●配給原点25,000点・原点30,000点
●トビ有り、持ち点が0点になるリーチもかけることが出来る。
●門前清自摸和と平和の複合はありとし、20符計算。
●親は和了と聴牌で連荘とし、ノーテンやチョンボの場合は親流れ。(途中流局は連荘)
●形式聴牌あり。(役なし聴牌も聴牌として認める)
●喰い替えなし。(同一牌とチーして完成面子の並びを替えたスジ牌を同巡内に切ることは不可)
●二翻縛りなし。(全局を一翻縛り)
●フリテンリーチあり。(ツモアガリのみ有効)
●ダブロン・トリプルロンあり。(親の和了は連荘、本場は全員、供託は放銃者からの上家取り)
●オープンリーチ、十三不搭、三連刻、四連刻、八連荘、大車輪、紅一色などの役はなし。
●花牌及び焼き鳥と一発賞・裏ドラ賞・役満賞などの祝儀(チップ)はなし。
●打牌が河に着いた瞬間から捨て牌となり、その後は一切手牌に戻すことは出来ない。
●和了は「ロン」又は「ツモ」と発声し、手牌を理牌し公開する。(リーチ時は裏ドラを全員に公開)
【流局及び連荘】
●最終局に親がノーテンやチョンボの場合は親流れとなり半荘は終了。
半荘終了時に供託分がある場合はトップ取りとする。
●最終局での親のアガリ止めは有り。
●連荘又は流局があるごとに積み場が加算し、一本場につき300点を和了点に加算。
●王牌は常に14枚残しとする。
【聴牌及びノーテン】
●カラテンは聴牌として認める。
但し、自分の手牌(副露も含む)で和了牌を全て使っている場合は不可。
●聴牌していても聴牌宣言をしない場合はノーテンとする。
●聴牌宣言は、東(親)→南→西→北の順に聴牌者は手牌を理牌し倒牌して公開する。
●聴牌と宣言したがノーテンだった場合は、チョンボとする。
但し、聴牌が不明で他者に確認を求めた時はチョンボとせず聴牌又はノーテンの処理をする。。
【途中流局】
●九種幺九倒牌は、親は配牌、子はチー・ポン・カンのない第一ツモ後の時。
他家のダブルリーチ後の九種幺九倒牌は認める。
●四風子連打は、チー・ポン・カン及び自分での暗槓がない開局一巡以内の打牌の時。
他家のダブルリーチ後の四風子連打は認める。
●四家立直は、4人目の立直宣言牌が他家の和了牌でない時。
●四開槓は、4回目の槓子の開示及び確認後(搶槓を優先)、打牌が他家の和了牌でない時。
一人で四槓子をしている時は、他家は5回目の槓は出来ない。
●途中流局になった場合は、ノーテン罰符なし及び供託分は供託の流局とし、親の連荘とする。
【チー・ポン・カン】
●チーとポン又はカンは発声が優先とし、発声がほぼ同時の場合はポン又はカンを優先とする。但し、ポン・カンがないのを確認したチーでポン・カンの発声が同時の時はチーを優先とする。
和了をチー・ポン・カンよりも優先とするが、著しく発声が遅れた場合は認めない。
著しく遅れた発声(ポン・カンも含む)は、次の人が打牌前であれば認め、打牌完了後は不可。
同時及び遅れた(著しくも含む)発声での和了及びチー・ポン・カンは罰則行為として扱わない。
他家の捨て牌に「ちょっと待って」等、進行を止めた場合は罰則行為として扱わない。
●次のツモ牌に触れた時は、ロン・チー・ポン・大明槓は出来ない。
●一度捨てた牌と同じ牌を鳴く喰い直しは認める。
●チー・ポンに連続してカンは出来ないが、カンの時は嶺上牌をツモ後に連続してカンが出来る。
●自分のツモ番がない時のチー・ポン・カンは海底牌及び河底牌を除き認める。
海底牌をツモった者は槓をすることが出来ず、河底牌をチー・ポン・カンをする事は出来ない。
●チー・ポン・カンの指示牌及び指示方向を間違えた場合、
発覚した時点で対局者全員が同意すれば指示表示を正しく修正して続行する。
指示牌ないし指示方向が不明及び対局者の不同意の場合は、現状を正当として続行する。
未訂正中にトラブルが生じた場合は、現状を正当として処理する。
☆明槓による嶺上開花時の責任払いはなしとし、ツモアガリとする。
☆槍槓時は槓が成立しないため、槓ドラは表示しない。
【リーチ】
●立直後暗槓はあり。
ツモ牌が暗刻牌と同一牌のみ認め、面子構成が変わる時(聴牌の形・送り槓も含む)は不可。
暗槓が出来る場合でもしなくても可。
●立直後でも和了牌の見送り(搶槓及びツモ切りも含む)は出来るが、以後はフリテン扱い。
●自分のツモ番がない時のリーチは出来ない。
●リーチ者は流局時に手牌を理牌し倒牌して公開する。
●リーチ宣言は、発声・宣言牌の横向け・供託立直棒(千点棒一本)の提供があって有効とする。
無発声・宣言牌を横にしない・供託立直棒の未提供のいずれかの場合は立直不成立とする。
但し、カラテン及びノーテンや立直後の不正な槓の時は、立直不成立とせず、チョンボとする。
立直宣言牌に対して、チー・ポン・カンがあった場合は、次巡の打牌を横向けにする。
●カラテンリーチ及びノーテンリーチは流局時チョンボとする。
リーチ時に誤ロンなどで和了放棄になり、流局時にカラテン及びノーテン時はチョンボとする。
●リーチの取り消しは出来ない。
立直の発声後宣言牌の打牌完了前であれば空行為とする。(罰符はなし)
●ダブルリーチは、チー・ポン・カン及び自分での暗槓がない開局一巡以内の打牌とする。
●リーチ一発と槍槓の複合は認める。
●一発の権利中に錯行為があった場合、一発の権利は消滅する。
【フリテン】
●フリテン時の和了は、ツモアガリのみ認める。
●同巡内フリテン時の和了は、自分のツモ番(又は副露)を経て打牌を行うまでフリテンとする。
【和了役】
●七対子の同一牌の4枚使いは認めない。
●嶺上開花と海底撈月の複合は認めないが、打牌が河底牌になった時の河底撈魚は認める。
●流し満貫は和了役として採用し、海底牌をツモった者が河底牌を捨てて流局した時とする。
自分が鳴いていてもリーチをかけていても可。
同一局で流し満貫の複数発生時は、親からの上家取り(東、南、西、北の順で一人)とする。
●人和は七対子の形でも認め、倍満とする。
チー・ポン・カンがない自分の第一ツモの経過がなく開局一巡以内の打牌による和了とする。
他の役との複合は認めないが、他の役が三倍満以上の場合は高め取りとする。
【包則】
●大三元、大四喜、四槓子に適用。
大三元:三種類目の三元牌をポン又は大明槓させた時。
大四喜:四種類目の風牌をポン又は大明槓させた時。
四槓子:三槓子完成者に生牌を大明槓させた時。
●ツモアガリは包者の一人払いとし、ロンアガリの場合は包者と放銃者の均等払いとする。
均等払い時での積み場の分は、放銃者の支払いとする。
●同巡内での同じ捨て牌で包則(二鳴き)になった場合、鳴かれた牌を捨てた者を包者とする。
●和了に包者が2人以上の場合は、役満毎に計算する。
●ダブル役満以上で包者がいる場合は、役満毎に計算する。
●包者がチョンボした時は、役満確定者に一人払い分の支払いとする。
包者以外がチョンボした時は、役満確定者に均等払い分の支払いとする。
【役満】
●数え役満あり。(13翻以上とし、役満と数え役満の複合は認めない)
●国士無双のみ、暗槓での搶槓を適用。
●国士無双13面待ちで捨て牌の中に幺九牌がある場合は、全てフリテンとする。
●天和、地和、字一色は七対子でも可。
●緑一色は、発が含まれてなくても可。
●四槓子は、雀頭の完成をもって和了とする。
●九連宝燈は、暗槓した場合は認めない。(立直後暗槓の時は、リーチ後の不正な槓とする)
●四暗刻単騎待ちなどの和了形や大四喜でダブル役満等になるのは認めない。
但し、小四喜・字一色など役満が複合した場合は、複合分をダブル以上の役満とする。
【見せ牌】
●見せ牌及び腰牌の規定はなしとする。
見せ牌の自己チェック申告時のみ、現物でのロンアガリ不可とする。
【トラブル】
●その他トラブルが生じた場合は、裁定人の裁定に従う。
●対局者同士で一旦了承した事項の再提訴は認めない。
|
|


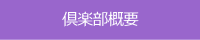
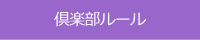
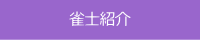
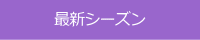
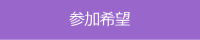


|







![]()
